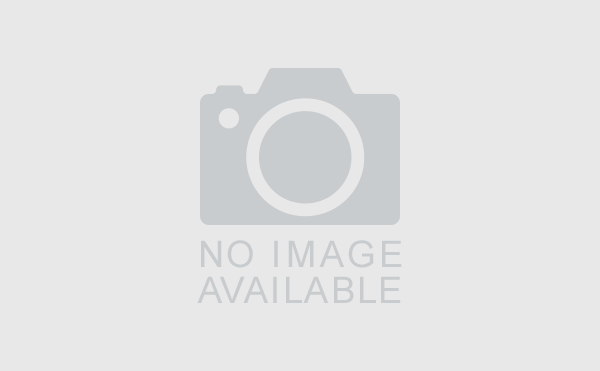盾無堰ってなぜ「たてなし」第1回
開催日:2024年10月16日(水)
盾無堰は徳島堰、朝穂堰と並んで山梨の三大堰の一つで茅ヶ岳の西南麓に位置する宇津谷、岩森、菖蒲沢、団子新居、大垈、龍地の各集落に生活用水、灌漑用水を供給しています。これらの地域は茅ヶ岳の火砕流によってできた傾斜の緩い台地状の地形で、水が乏しく、作物などが育ちにくい環境でした。
摂津の国の出身で江戸の浪人(商人という説も)野村久左衛門宗貞が宇津谷村に隠棲していた時に、住民たちが水の確保に苦労しているのを見かねて堰の開削に思い至ったのが盾無堰のはじまりといわれています。宗貞は自ら測量、設計、資金調達を行い甲府藩主徳川綱重の許可を得て寛文六年(1666)に開鑿に取り掛かりました。明野村小笠原(現北杜市明野町)の塩川から取水し末端の龍地までの17Kmをわずか36mの標高差でつなぐという緩やかな勾配でできています、これは工事費用を節約するため勾配を緩やかにし距離を短くするためです。そのため上流では2000分の一程度の勾配のところもあり安定に水を流すのは現在の技術をもってしても大変なことだったと思われます。
「盾無」の名は堰が盾無原(現在の韮崎市韮崎町上の宮から穂坂町のかけての辺り)を通っていたことから名づけられたといわれていますが、盾無原の起源には諸説あり、あまり明らかではありません。
現在の盾無堰は何度も改修、変更が繰り返され権現沢までの水路の多くが隧道となり開鑿当時の原型はあまり残っていないようですが、ところどころで顔を出す水路と周りの地形を見ると当時の工事の困難さが想像できます。江戸時代どのようにしてここに水を通したのか考えてみましょう。
・コース:JR穴山駅(トイレ)→三村橋→盾無堰頭首工(取水口)→明野町三之蔵→駒井橋→JR韮崎駅(トイレ)
「コースマップ」「グーグルマップ」
・距 離:約 9Km
・集 合:穴山さくら公園駐車場(JR穴山駅前) 9時30分
上り 小淵沢駅8:48 穴山駅9:16 下り 甲府駅8:50 穴山駅9:11
・解 散:JR韮崎駅 13時ころ
・参加費:会員300円 一般500円
・持ち物:飲み物、雨具、ウオーキングダイアリ(会員のみ)、保険証、その他
・担当者:大嶋俊壽 多賀純夫
・その他:途中トイレはありません、後半は塩川沿いに歩きます、緊急の場合は駒井で国道141号線に出て少し戻ります
昼食は少し遅くなりますが韮崎駅周辺で各自で摂ってください、途中空腹が心配な方は各自で準備してください。